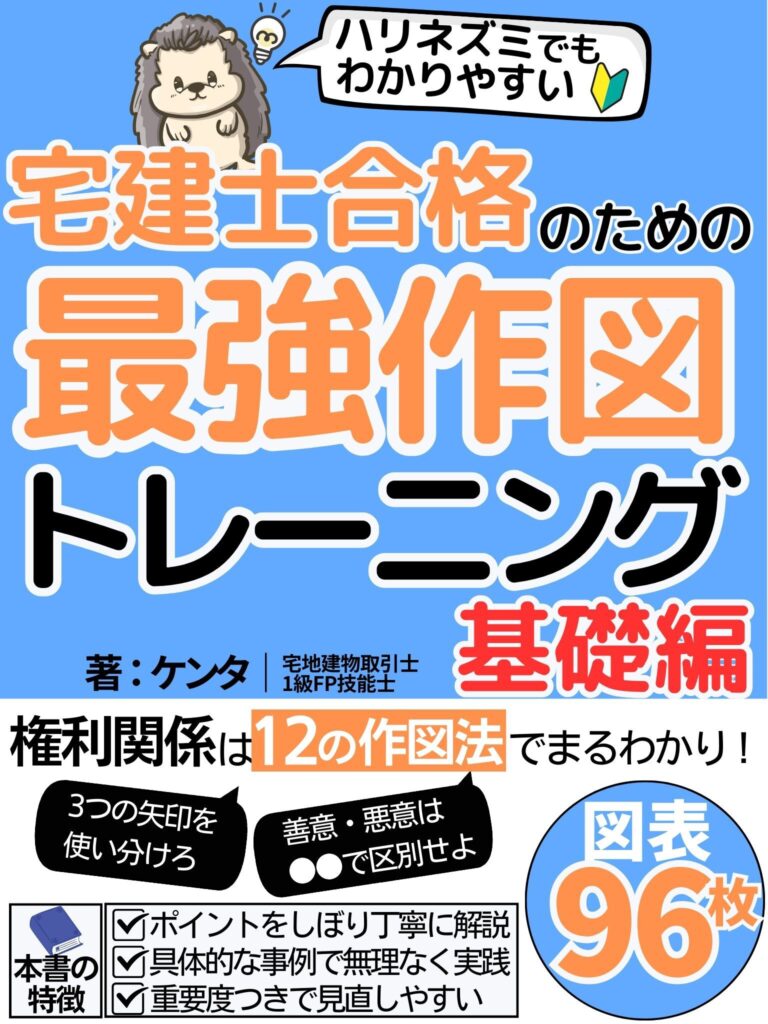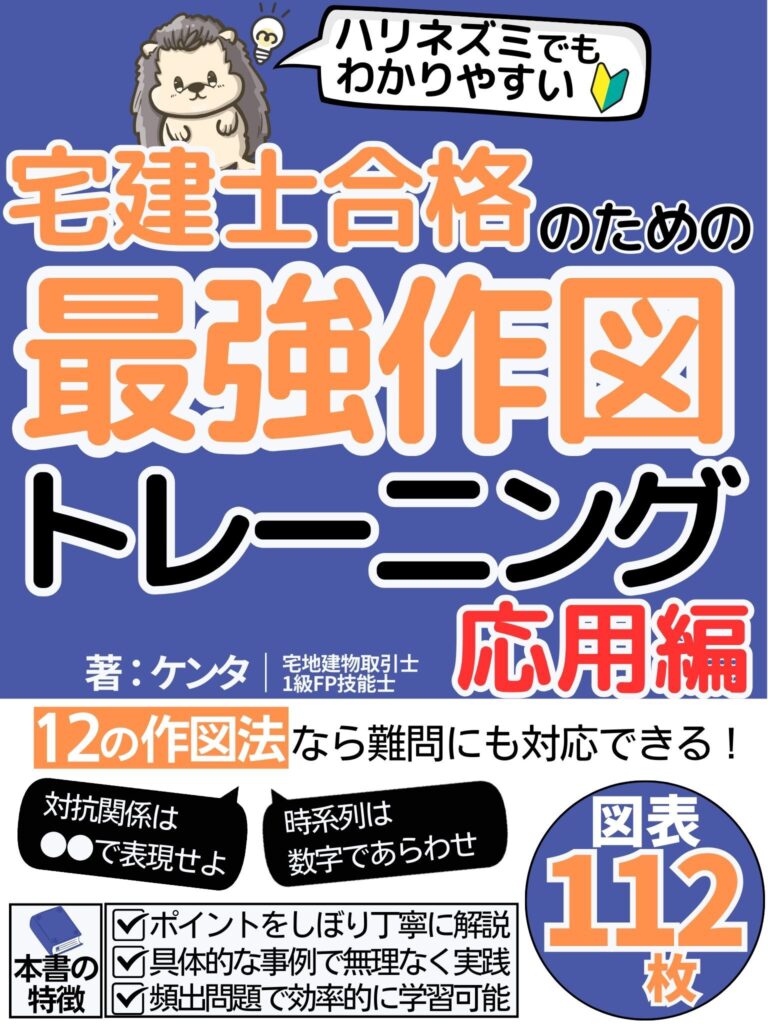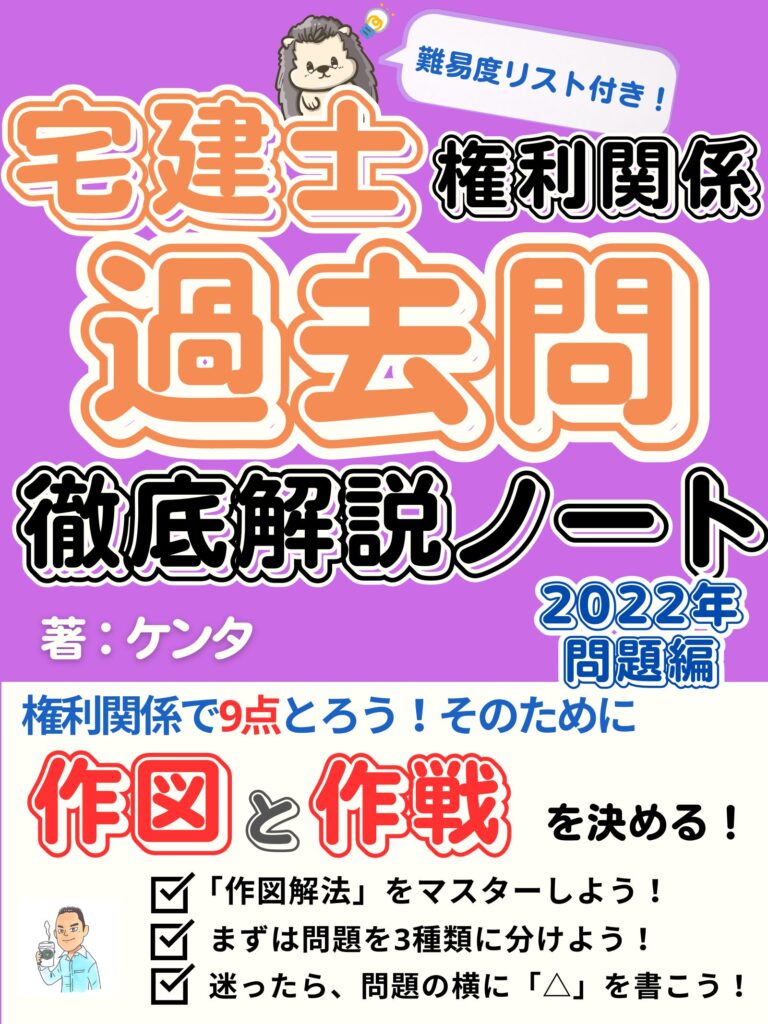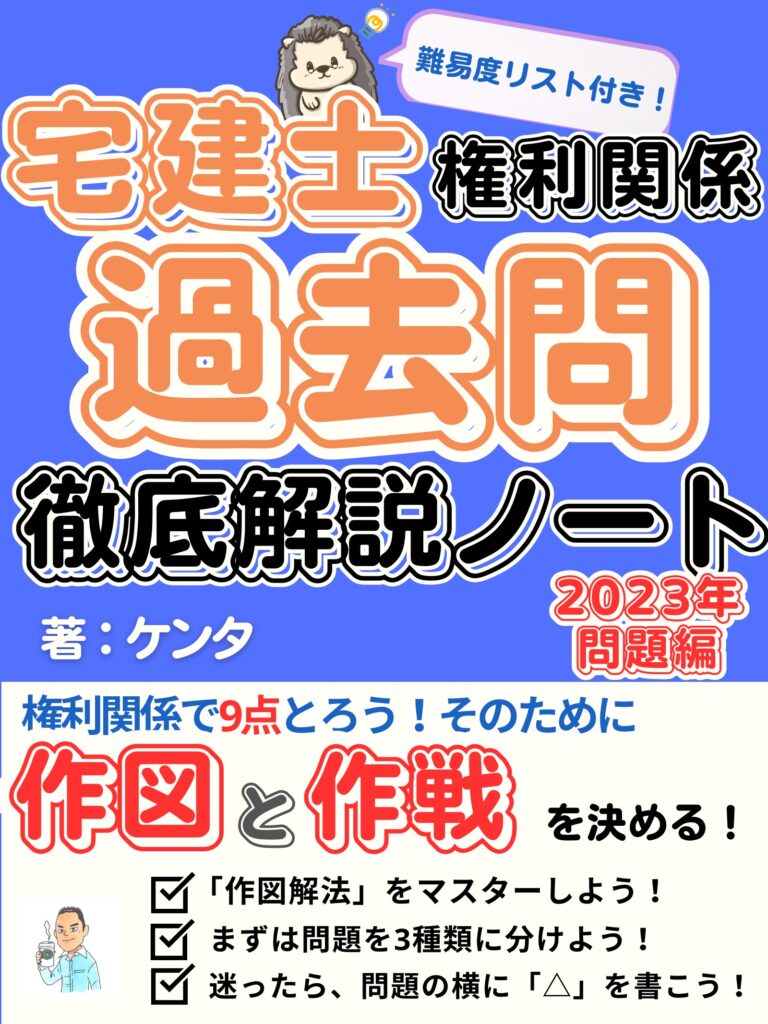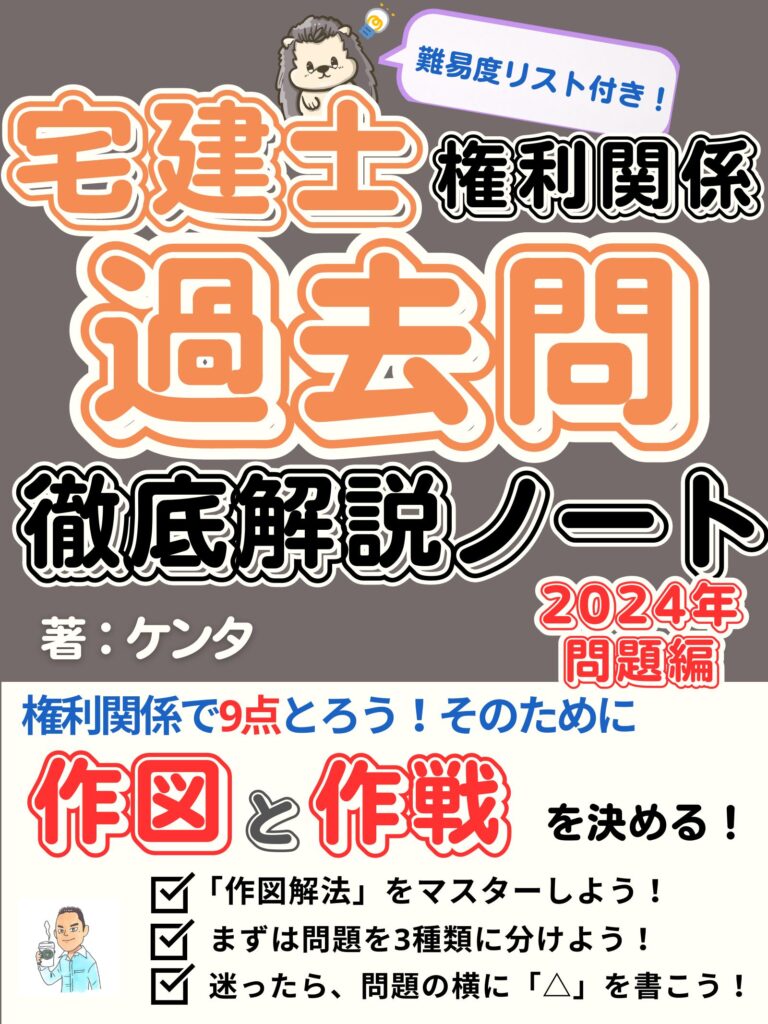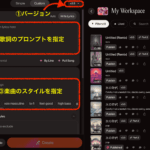宅建士を受験したらすぐにFP2級を取っておいたほうがオトク。
宅建士の試験が終わってなんか気が抜けたよ。
それはもったいない……
宅建士を受験した人はすぐさま翌年1月のFP受験にトライしたらいいと思うのですよね。
そもそも宅建士の本試験は10月なのですが、結果発表が12月初旬なんですよね。
合格ボーダー近辺だと約40日間も合否を気にしないといけないという生き地獄。
関連記事:宅建士試験で合格ボーダー近辺の私は1ヶ月も生殺し状態。【2019年秋】
宅建士を受けたらFPの簡単さに驚愕した。
個人的な所感ですが、宅建士試験の歪みきった問題を乗り越えたあとFPの試験問題を解くと難易度の違いに驚きます。
たとえると「プロ野球の打者が絶好調のとき、ピッチャーの投球がとまって見える」という感じ。
問題を解いているときに選択肢の正誤が透きとおって見えるような感じです。
宅建士のときはこんな状態にならなかったんですよ。
2択まで絞れるけど最後の1択を決めかねないというモヤモヤした感じがあります。
FPの場合、特に3級は20時間ほどを費やせればクイズ感覚で解けるはずです。
現に私は50時間ほどでストレート合格しました(勉強しすぎ、効率悪すぎという説あり)
関連記事:FP3級に一発合格!次に狙う資格は何がいいのか問題
今はFP2級の勉強をしているのですが、野球でいうと「球がとまって見える状態」。
特に多くのFP受験生が苦しむ「不動産」の分野は宅建士受験生にとってアドバンテージになるんですよね。
不動産の10問のうち8割は余裕でとれます。
宅建士を勉強したらFPの25%を網羅できている。
じつは宅建士とFPというのはとても相性がいいんですよね。
勉強内容が重複する部分が多いからです。
FPの科目は次の6科目となっています。
2)リスク管理
3)金融資産運用
4)タックスプランニング
5)不動産
6)相続・事業承継
この中で宅建士の試験範囲でカバーしているのは「不動産」と「相続」と「タックスプランニング」の一部です。
宅建士をまじめに勉強していれば「不動産」分野は問題集を一回転していればOKかなと思います。
とくにFP3級の場合は1時間くらい復習すれば大丈夫!
不動産分野の対策は不要。
このように宅建士とFPの重複する分野はだいたい4分の1を占めます。
FP2級の勉強時間もかなり削減できます。
ざっくりとこんな流れ。
➡️FP3級(合格)
➡️宅建士(2回目合格:36点)
➡️FP2級(来年1月)
勉強の習慣もついてきたので、完全独学で試験対策に取り組めています。
もし独学で不安がある場合は、さくっとオンラインの通信講座で勉強しておくのがおすすめ。
スマホで勉強できます。
すきま時間に勉強するのに大きなアドバンテージとなる「スタディング」 を試してみるのもいいでしょうね。
難易度の高くない資格はスマホでさくっと勉強するのがスマートです。
FPではタックスプランニングが最優先です。
個人的にはFP技能士の醍醐味は「タックスプランニング」にあると思います。
税制を理解していることを前提として「年金」「投資」「保険」の提案が成り立つのです。
あと、試験対策上もタックスプランニングから派生している問題も多いので、所得税を中心として法人税、相続税について知識を深めると得点しやすいですね。
最初はあくまで「所得税」が最優先!
まとめ:せっかくだから宅建士を受けたらFPも取っておこう
FP2級は資格としてもそれほど難易度が高いわけではなく、特に独占業務があるわけではありません。
ただ、FPの知識は生きていく上で決してムダにはなりません。
お金について体系的に学ぶよい機会です。
せっかく宅建士の勉強をしたのであればついでにFPも勉強しておきましょう。
きっと相乗効果を実感できるはずです。
ぜひ拙著もご参考に!
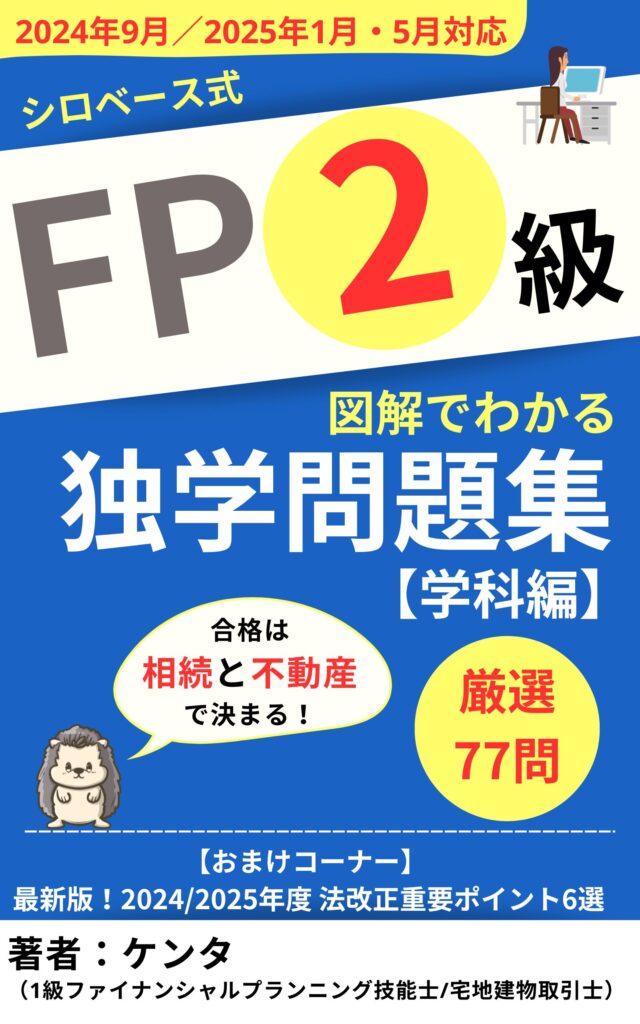
★ご案内
多くの宅建士受験生が苦手とする「権利関係」。
「権利関係の14問が合否をわける!」といっても過言ではないほど重要なジャンルです。
そこで、権利関係に特化したテキストと問題集合計5冊をKindleで発売中!
ちなみに、Kindle Unlimitedなら月額980円で200万冊以上が読み放題。
30日間の無料体験もありますので、お試しください!
①「宅建作図(基礎編)(応用編)」
「基礎編」では「12の作図ルール」を紹介し、「応用編」では「債権」「物権」「賃貸借」という宅建士の頻出パートを図解しています。まずは、基本的な作図パターンをトレーニングしましょう!
②「宅建士過去問(権利関係)徹底解説ノート(2022年〜2024年問題編)」
権利関係14問のうち9問以上正解するため過去問を研究した成果を「徹底解説ノート」として発売中!
各問題の難易度や正解パーセンテージを記した「難易度リスト」も記載していますので、ご参考にしてください。
他にも「スリランカアーユルヴェーダ旅行記」や「睡眠薬の断薬記録」などの電子書籍も発売しているのでぜひご覧ください!
*「Kindleアンリミテッド」では無料で読めますので、ぜひ!
FP相談サービスなどなんでもご相談にのります!
詳しくはこちらから!
この記事を書いたのは私です

-
いまは兼業会社員ですが、2025年中に行政書士事務所を開業予定!
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多業界ですべての管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)
【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。
【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。
【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。
最新の投稿
 旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由
旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由 家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう!
家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう! 旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。
旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。 健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。
健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。