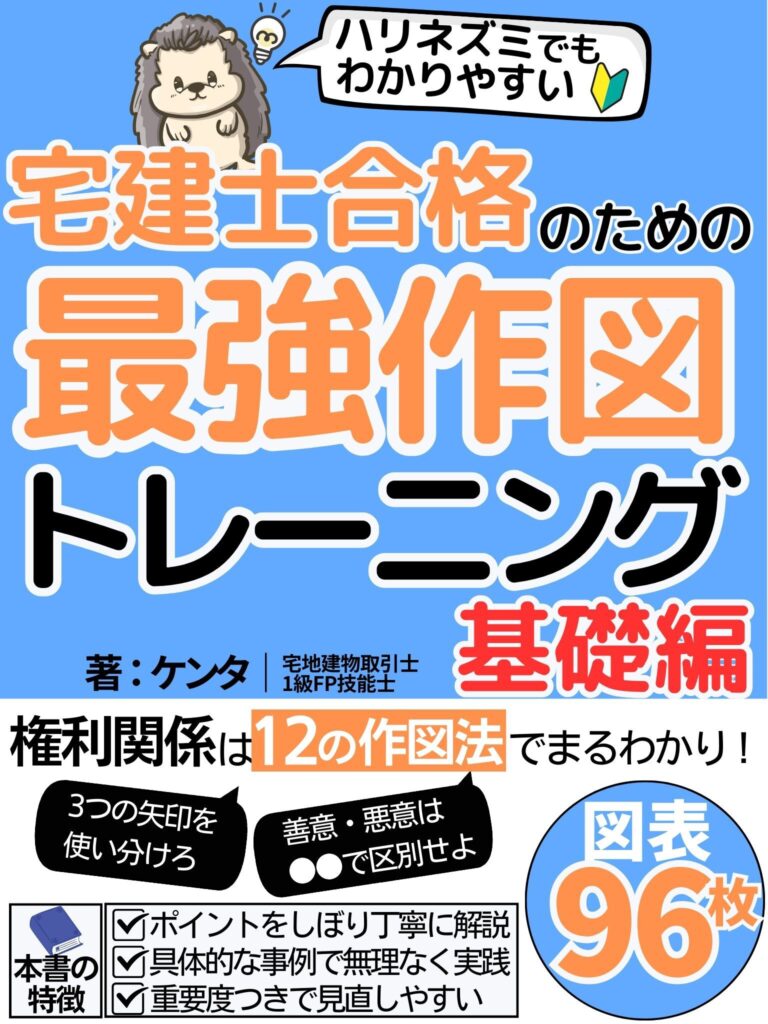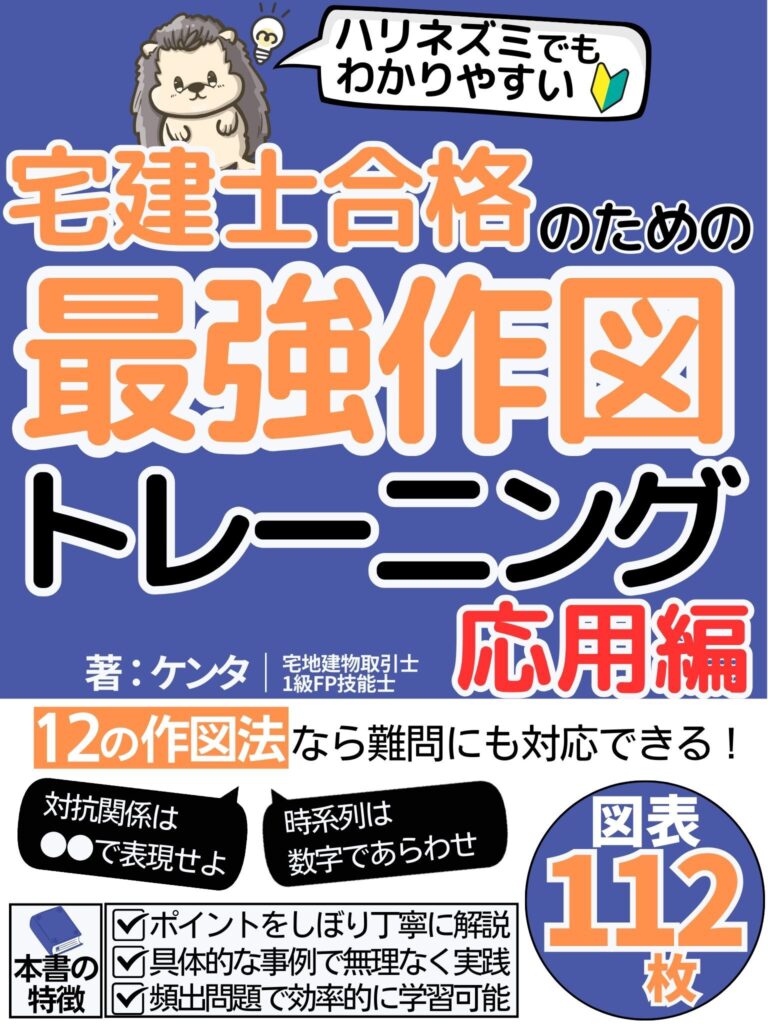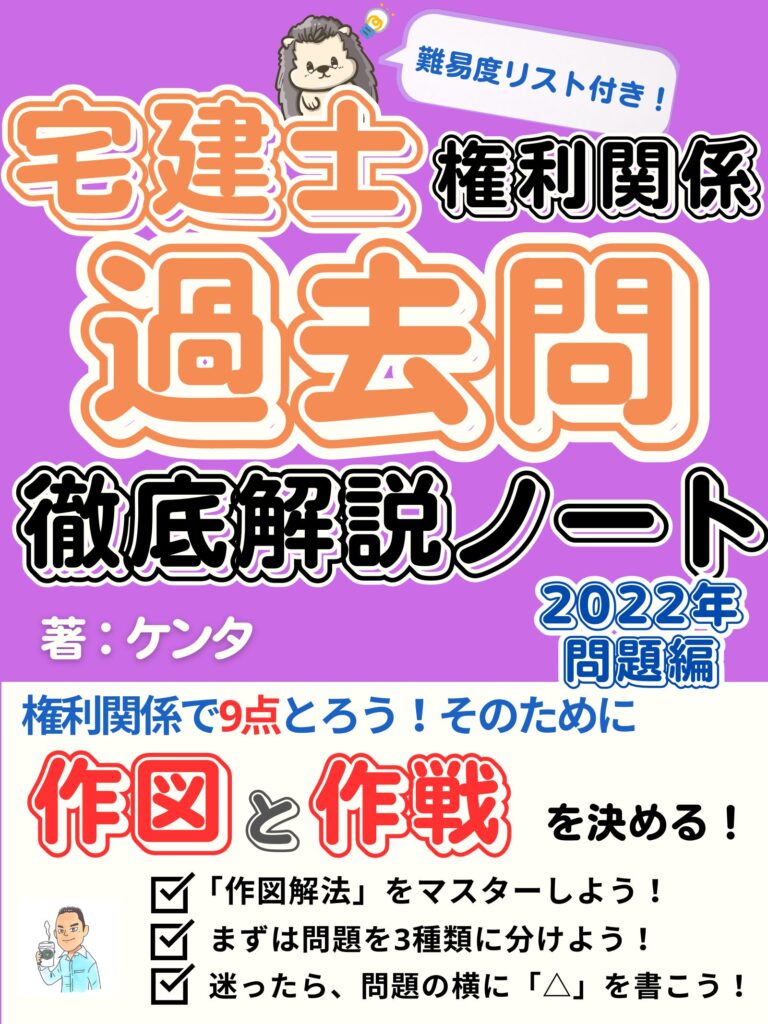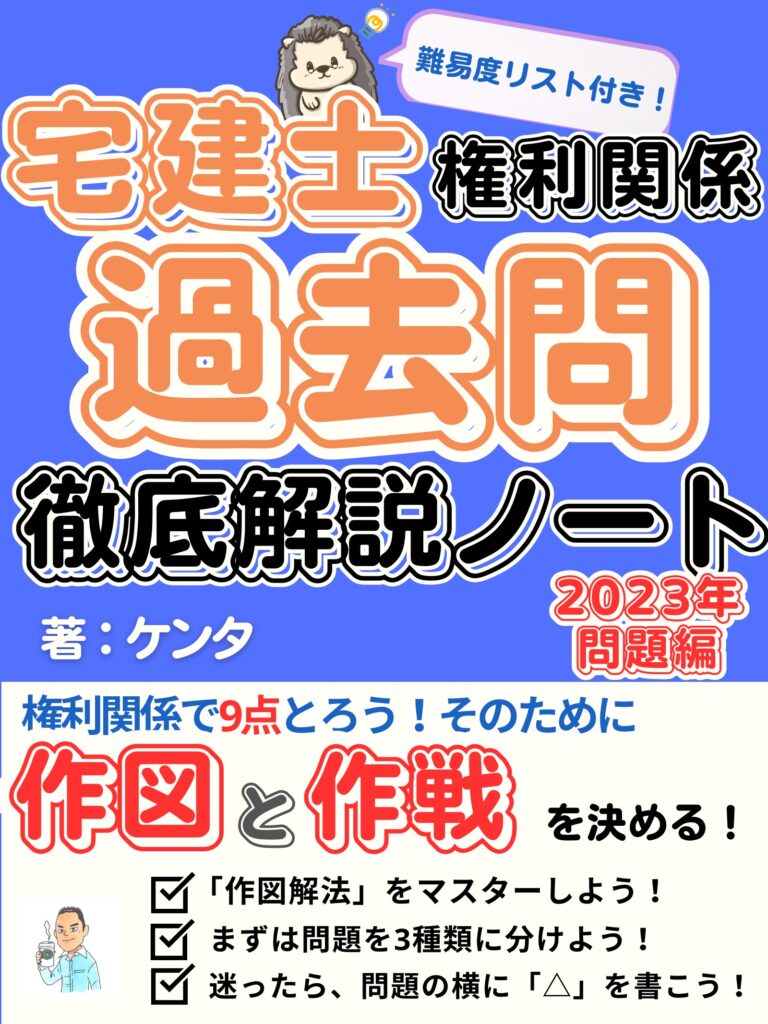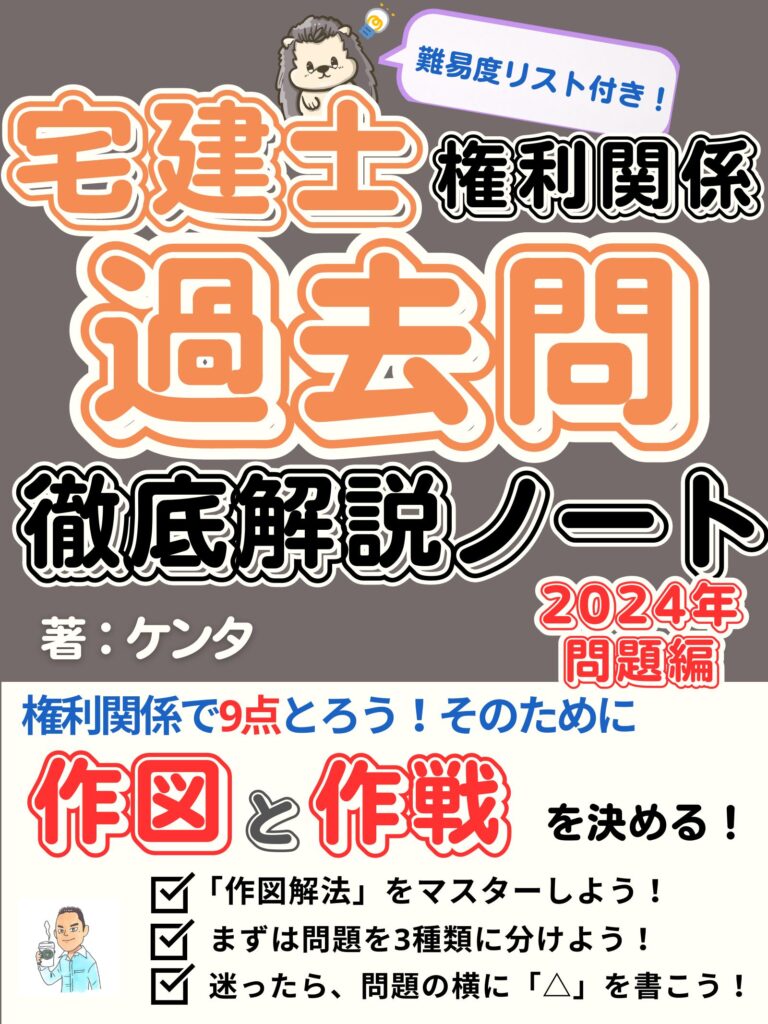私が宅建士試験に失敗した理由を切々と語る【2018年秋】
2018年にはじめて宅建士の本試験を受験しました!
Twitterで当日の様子を実況中継していましたが、もはや精も根も尽き果てました。
過去記事:【実況】2018年宅建試験当日の一部始終を振り返ってみた。
そして、翌日の月曜日はほぼ廃人状態でした……。
なぜなら、予備校が出している解答速報で自己採点をしたところ、結果が分かってしまったからです。
宅建試験をおそるおそる自己採点したら2択にしぼった選択肢がことごとく間違っていて、なんと32点/50点。。。 よ、余裕で落ちました。 — ケンタ (@kentasakako) 2018年10月21日
落ちました!
どんなに楽観的にみても合格ラインは35点に対して32点なので、確実に落ちましたね。
ということで今回は宅建試験に落ちた理由を考えてみました。
(1)完全独学のため応用がきかなかった。
宅建士は周囲でも結構取得している人がいるので、簡単だと思われがちなんですよ。
だから「なるべくコストをかけることなく独学で大丈夫でしょう」と思ってしまったのです。
そして、必要最低限のテキストと問題集と過去問だけで対応しようとしたのです。
しかし、過去記事にも書いたように私は法律の勉強をしたこともなければ、不動産関係のバックボーンを備えたこともありません。
過去記事:不動産業界と関係ないのに、宅建士の資格に挑戦している5つの理由。
完全独学だと、自分の分からないところを追求することなく我流を貫くしかありません。
試験本番でちょっとだけひねった問題が出るだけで、私は全く対応できませんでした。
(2)「権利」が弱すぎる。民法がボロボロ。
ちょっと内容に立ち入ってみると、特に「権利関係」問題が絶望的な状態です。
14問中正解したのはなんと5問だけ!
9問も間違えました!!
試験前は半分の7問できればなんとかなると思っていたのですが、
自己採点中に目の前が真っ白になりました。
やはり、法律初学者にとって民法は最難関だと実感しました。
(3)独学だと勉強効率が悪い。
独学のメリットはなんといっても、コストが安いことと自由なスタイルで勉強できることです。
しかし、モチベーションを維持する難しさに対処しないといけません。
さらに、勉強に無駄な工程が発生したりするので、忙しい人ほど独学は止めたほうがいいかもしれません。
急がば回れといいますし、効率的な勉強方法を確立したほうがいいですね。
ちなみに私は試験まで276時間も宅建士の勉強に費やしましたが、ものの見事に無に帰りました。
関連記事:宅建士の勉強時間が200時間を超えたときの正直な感想。
さて、来年に向けて頑張りましょうか。
(追記)
その翌年に無事合格しました!
★ご案内
多くの宅建士受験生が苦手とする「権利関係」。
「権利関係の14問が合否をわける!」といっても過言ではないほど重要なジャンルです。
そこで、権利関係に特化したテキストと問題集合計5冊をKindleで発売中!
ちなみに、Kindle Unlimitedなら月額980円で200万冊以上が読み放題。
30日間の無料体験もありますので、お試しください!
①「宅建作図(基礎編)(応用編)」
「基礎編」では「12の作図ルール」を紹介し、「応用編」では「債権」「物権」「賃貸借」という宅建士の頻出パートを図解しています。まずは、基本的な作図パターンをトレーニングしましょう!
②「宅建士過去問(権利関係)徹底解説ノート(2022年〜2024年問題編)」
権利関係14問のうち9問以上正解するため過去問を研究した成果を「徹底解説ノート」として発売中!
各問題の難易度や正解パーセンテージを記した「難易度リスト」も記載していますので、ご参考にしてください。
他にも「スリランカアーユルヴェーダ旅行記」や「睡眠薬の断薬記録」などの電子書籍も発売しているのでぜひご覧ください!
*「Kindleアンリミテッド」では無料で読めますので、ぜひ!
FP相談サービスなどなんでもご相談にのります!
詳しくはこちらから!
この記事を書いたのは私です

-
いまは兼業会社員ですが、2025年中に行政書士事務所を開業予定!
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多業界ですべての管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)
【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。
【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。
【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。
最新の投稿
 人生について2026年1月4日2026年の目標を4つ立ててみた
人生について2026年1月4日2026年の目標を4つ立ててみた 資産運用2025年12月31日インフレ時代だし、老後貯金をいったんやめてみる。
資産運用2025年12月31日インフレ時代だし、老後貯金をいったんやめてみる。 税金2025年12月27日会社を辞める前に「市役所」へ。国民健康保険の仕組みを知ったら今後の日本がちょっと怖くなった話。
税金2025年12月27日会社を辞める前に「市役所」へ。国民健康保険の仕組みを知ったら今後の日本がちょっと怖くなった話。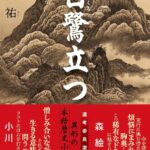 おすすめの本と映画2025年12月25日「タイパ病」になったら、「白鷺立つ」で千日回峰をイメージしてみよう!
おすすめの本と映画2025年12月25日「タイパ病」になったら、「白鷺立つ」で千日回峰をイメージしてみよう!