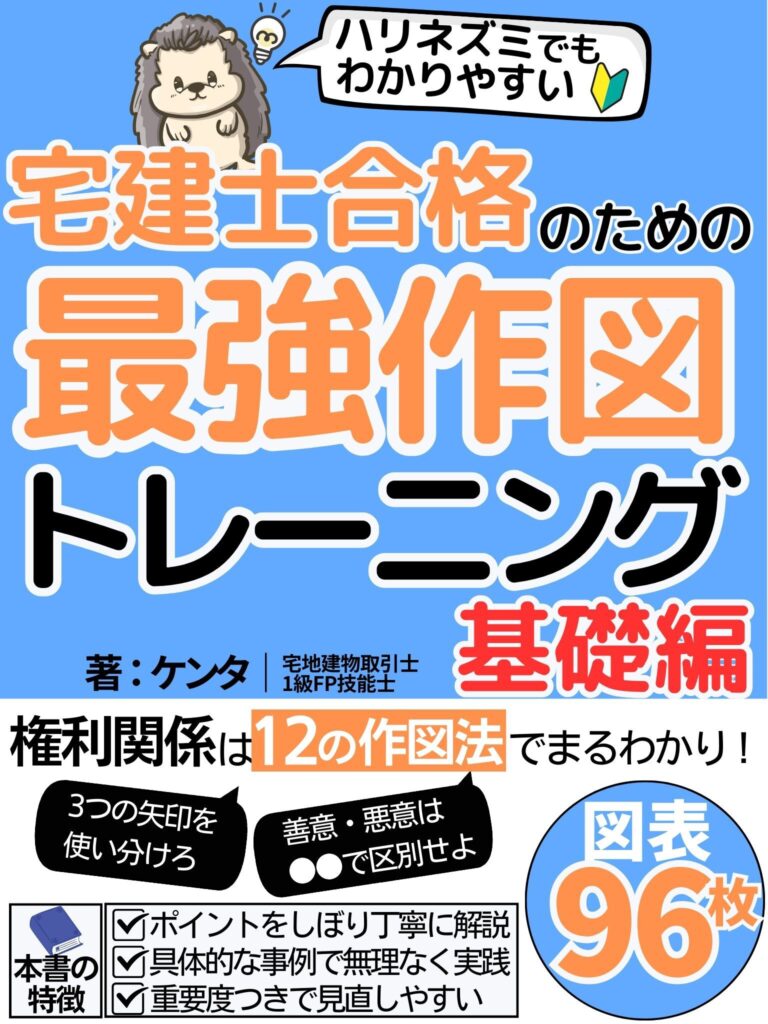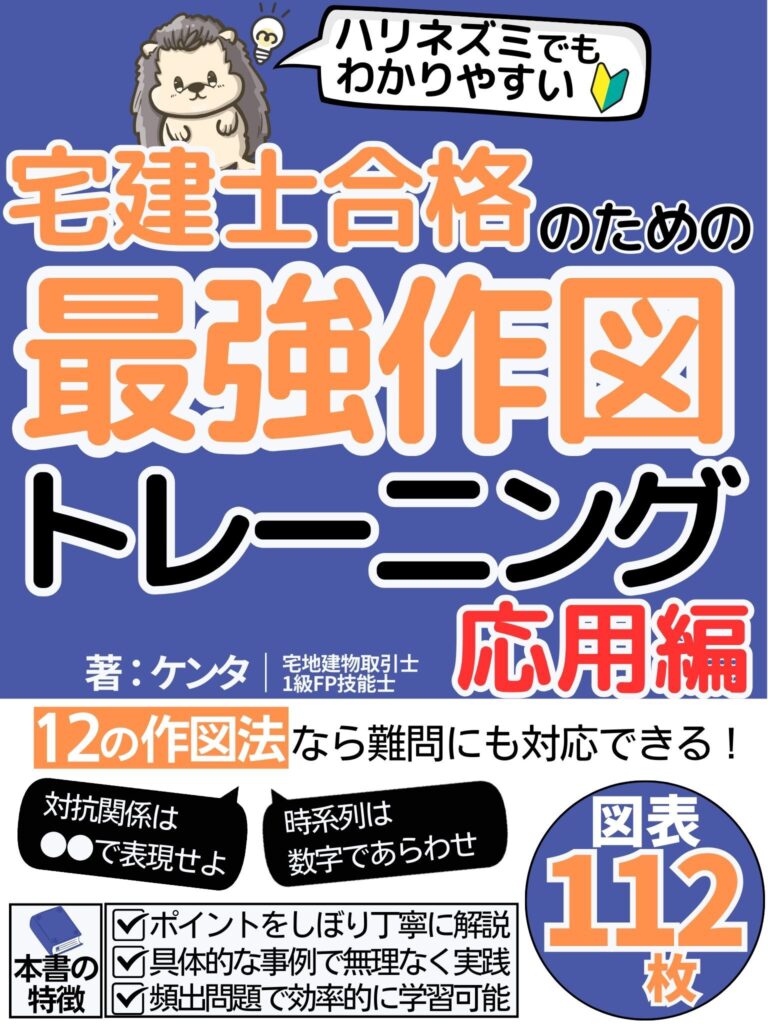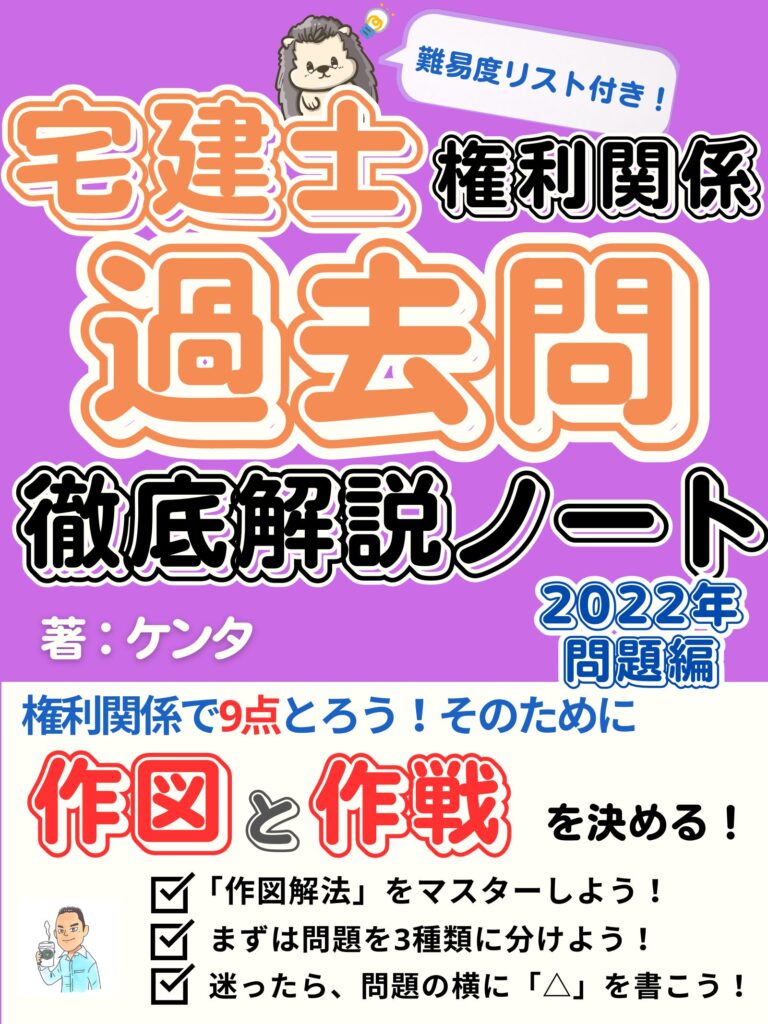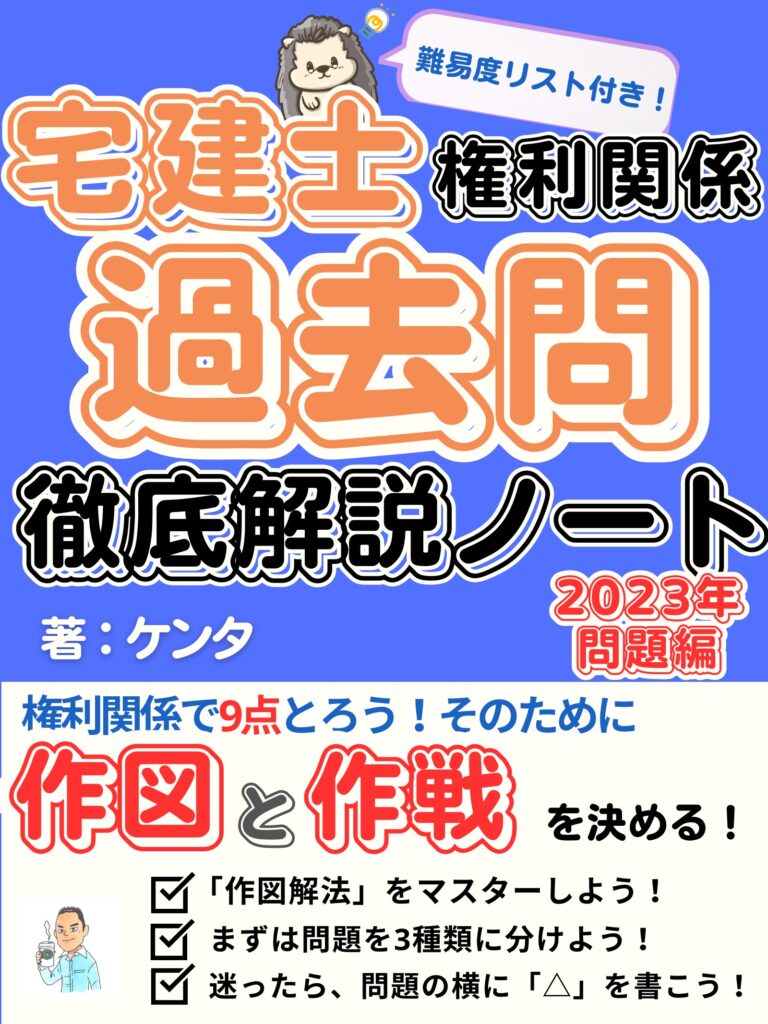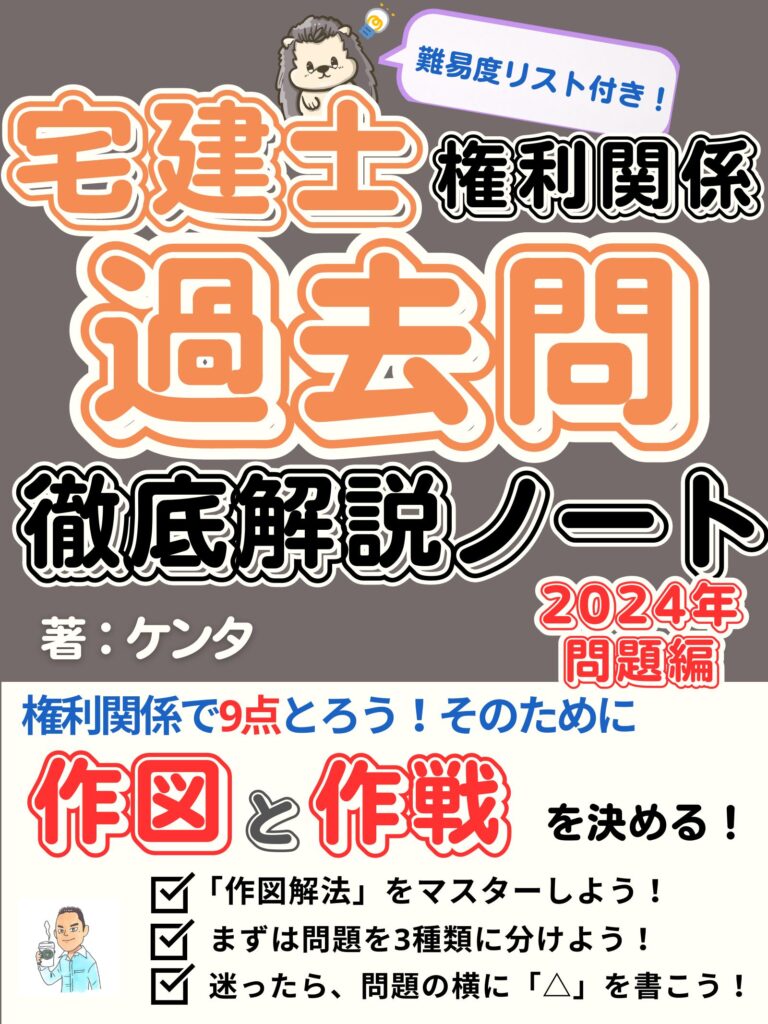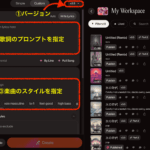宅建士の独学はハードすぎる。【理由は3つ】
私は今年(2019年)こそ宅建士に合格して次のステップに進みたいなと思っています。
ところで最近ブログやSNS経由で「私も宅建士を独学しています!」との声をいただくのですが、正直言って独学はおすすめしません。
独学は単純にコスパが悪いからです。
特に初学者にとっては宅建士の勉強をするなら独学はやめたほうがいいかもです。
その理由は3つほどあります。
(1)独学は時間を無駄にしやすい
恥ずかしい過去の話をします。
昨年(2018年)に宅建士を受験したとき、250時間以上を独学に費やしました。
その結果は残念ながら不合格。
過去記事:【落ちた】私が宅建試験に失敗した理由を切々と語る【2018年秋】
今年になって心機一転、2月から「資格スクエアの宅建士講座」という通信講座で宅建士の勉強をしています。
便利な点としては、スマホでどこでも勉強できますし、早送りすると時間もセーブできます。
ただ、動画配信だとデータ通信量がかなり消費されるので音声だけの配信にして調整しています。
今は動画で勉強する時代ですね。
さて話をもどします。
今考えると「250時間も勉強して宅建士試験に合格できなかった」というのはかなりの痛手です。
なにより時間がもったいない。
去年、私は市販の参考書や問題集を利用して勉強していました。
もちろん、それで合格できる人はたくさんいるのでしょうが、法律初学者にとってはハードルが高いんですよ。法律の壁にぶちあたるのです。
そこにきて通信講座を受けると、講師が丁寧に具体的に説明してくれるのでとてもありがたいですね。
(ちなみに資格スクエアの田中講師の説明はめちゃくちゃ分かりやすいです。)
ムダな勉強時間はなるべくカットしましょうね。
(2)民法を独学で理解するのは時間がかかる。
じつは宅建士の試験で合否を分けるのは民法だといっても過言ではありません。
宅建士の受験初心者はよくこのように考えがちです。
宅建士試験は50問中20問も宅建業法の問題だから宅建業法さえ満点だったらなんとか合格できるでしょう?
じつは私もそう思っていました。
宅建業法の出題が20問、権利関係が14問という問題数だとどうしても宅建業法を優先しがちなんですよね。
でもそれではダメなんです。
そもそも「宅建業法」というのは「民法」の特別法にあたる存在です。
世の中のルールとしてはあくまでも「民法」が一般法として原則となり、それをベースとして「宅建業法」という特例ルールが成り立っているのです。
だから「宅建業法」だけ勉強して「民法」を勉強しないというのは優先順位が逆なんですよね。
まずは「民法」という一般ルールを理解してから「宅建業法」をおさえるというのが本来の手順です。
さて、民法を独学でマスターしようとする人もいるでしょう。
しかし、これがめちゃくちゃ難しいんですよ。
まず基礎的な法律用語を理解する必要がありますし、問題の状況を把握するために「図解」する手法を用いるのが受験の常識となっています。
独学ではこのような「受験常識」を教えてくれません。
テキストにはのっていないことがたくさんあるのです。
(3)本当の理解がなければ意味がない。
試験に落ちた私が言えることではないのですが、実力をともなわずに宅建士に受かってもあまり人生に役立たないと思うんですよね。
まぐれで受かっても意味ないんですよ。
ネットでの情報を見ると「国家資格を取得するために宅建士試験さえパスすればいい」という意見が多いですが、本当にそうでしょうか?
個人的な意見としては、法律(とくに民法)の深い理解がないと資格取得の成果はうすいと思います。
たとえば「事務管理」。
2018年に出題された権利関係の「事務管理」の問題(平成30年本試験の第5問)、受験された皆さんわかりましたか?
私はさっぱり分かりませんでした!
「事務管理」なんていう項目は宅建士のテキストにはほとんど掲載されていないんですよね。
それもそのはず民法には1000を超える条文がありますのですべてを網羅することなんてできないのです。
ただ、「事務管理」というのは民法の中では基本的な概念。
じつは宅建士としては知っておいて当然な知識のはずです。
せっかく宅建士を勉強しているのに民法に疎かったらもったいないですよね。
民法は勉強しておいて損はないですよ。
まとめ:宅建士の独学はハード
自戒をこめてまとめます。
法律初学者は完全独学はかなり困難です。
独学では「え、法律ってどこまでおさえればいいの?」と不安になりますが、スクールや通信講座なら勉強範囲を絞ってくれますので、スムーズに学習できます。
ただ、自分のケースを振り返ると、独学により純粋に民法を深掘りできたと感じています。
勉強が好きで時間がある方は、独学をつうじて民法の研究を楽しむのも1つの手かも。
めったにいないだろうけど……
★ご案内
多くの宅建士受験生が苦手とする「権利関係」。
「権利関係の14問が合否をわける!」といっても過言ではないほど重要なジャンルです。
そこで、権利関係に特化したテキストと問題集合計5冊をKindleで発売中!
ちなみに、Kindle Unlimitedなら月額980円で200万冊以上が読み放題。
30日間の無料体験もありますので、お試しください!
①「宅建作図(基礎編)(応用編)」
「基礎編」では「12の作図ルール」を紹介し、「応用編」では「債権」「物権」「賃貸借」という宅建士の頻出パートを図解しています。まずは、基本的な作図パターンをトレーニングしましょう!
②「宅建士過去問(権利関係)徹底解説ノート(2022年〜2024年問題編)」
権利関係14問のうち9問以上正解するため過去問を研究した成果を「徹底解説ノート」として発売中!
各問題の難易度や正解パーセンテージを記した「難易度リスト」も記載していますので、ご参考にしてください。
他にも「スリランカアーユルヴェーダ旅行記」や「睡眠薬の断薬記録」などの電子書籍も発売しているのでぜひご覧ください!
*「Kindleアンリミテッド」では無料で読めますので、ぜひ!
FP相談サービスなどなんでもご相談にのります!
詳しくはこちらから!
この記事を書いたのは私です

-
いまは兼業会社員ですが、2025年中に行政書士事務所を開業予定!
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多業界ですべての管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)
【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。
【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。
【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。
最新の投稿
 旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由
旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由 家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう!
家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう! 旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。
旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。 健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。
健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。