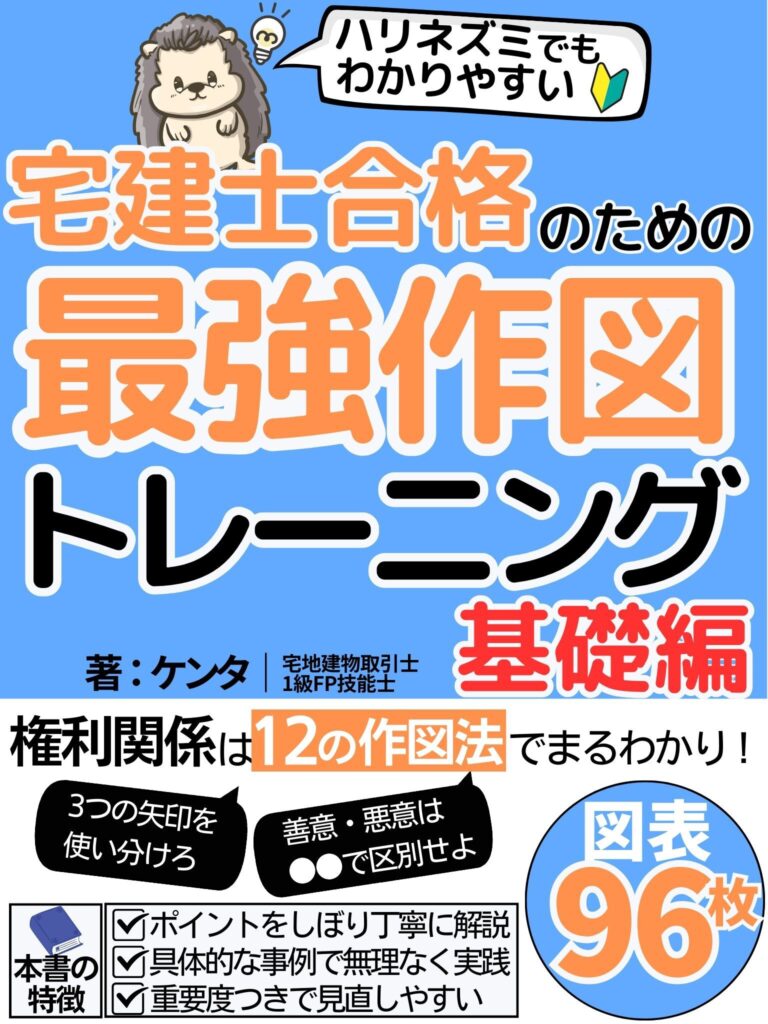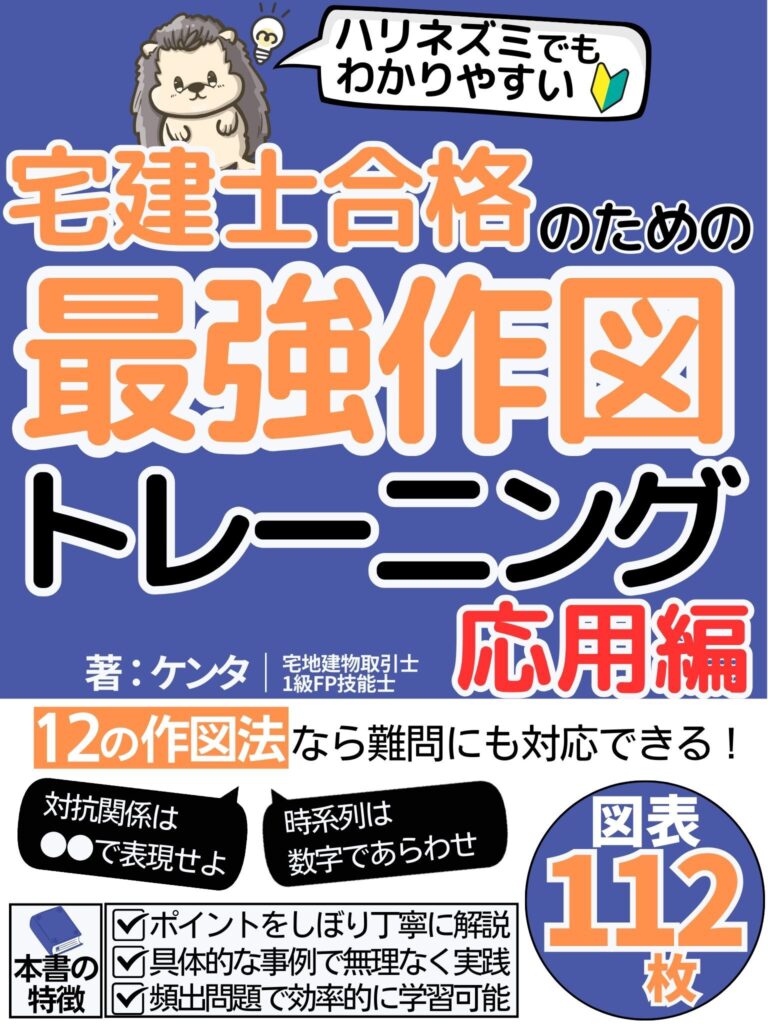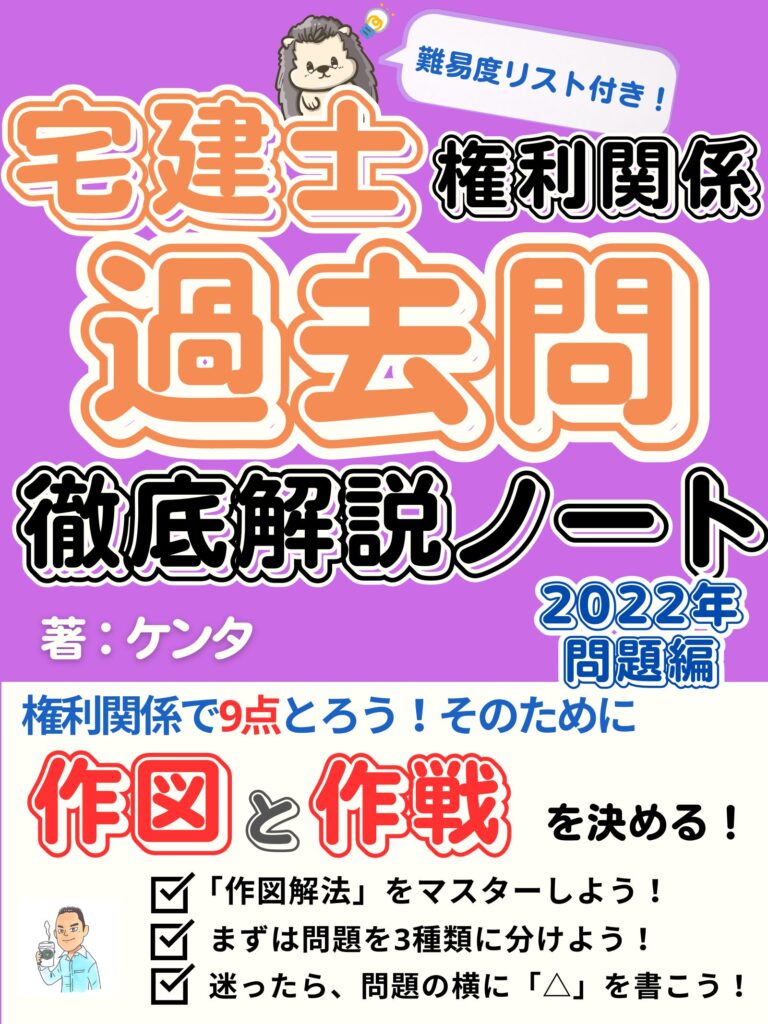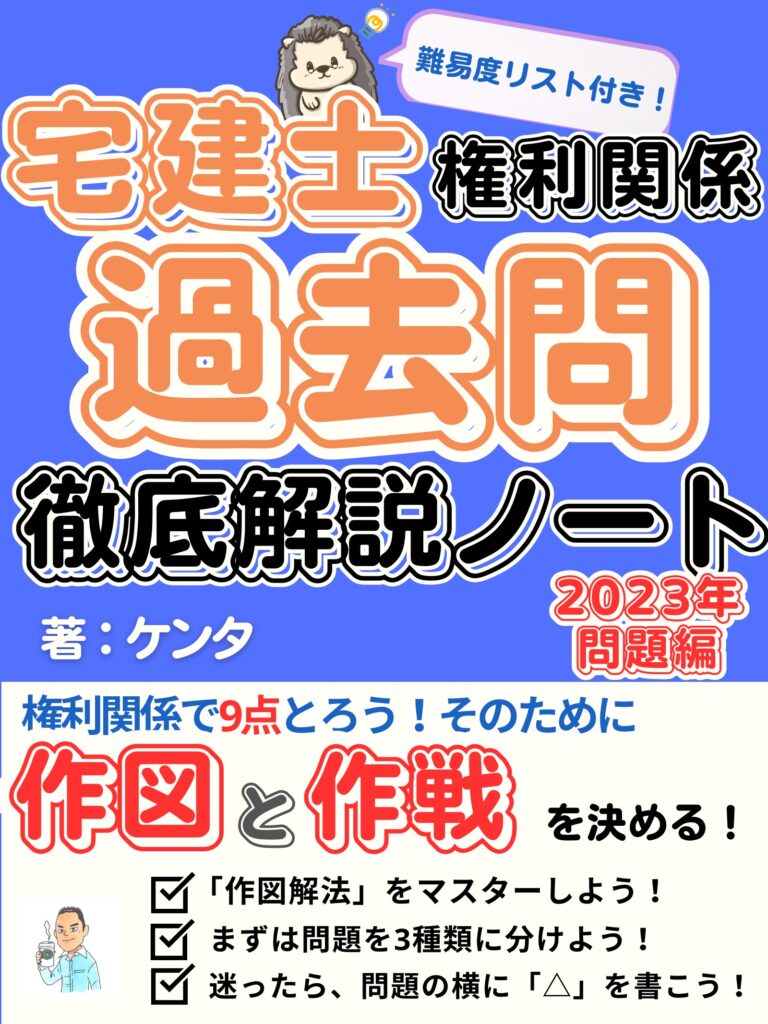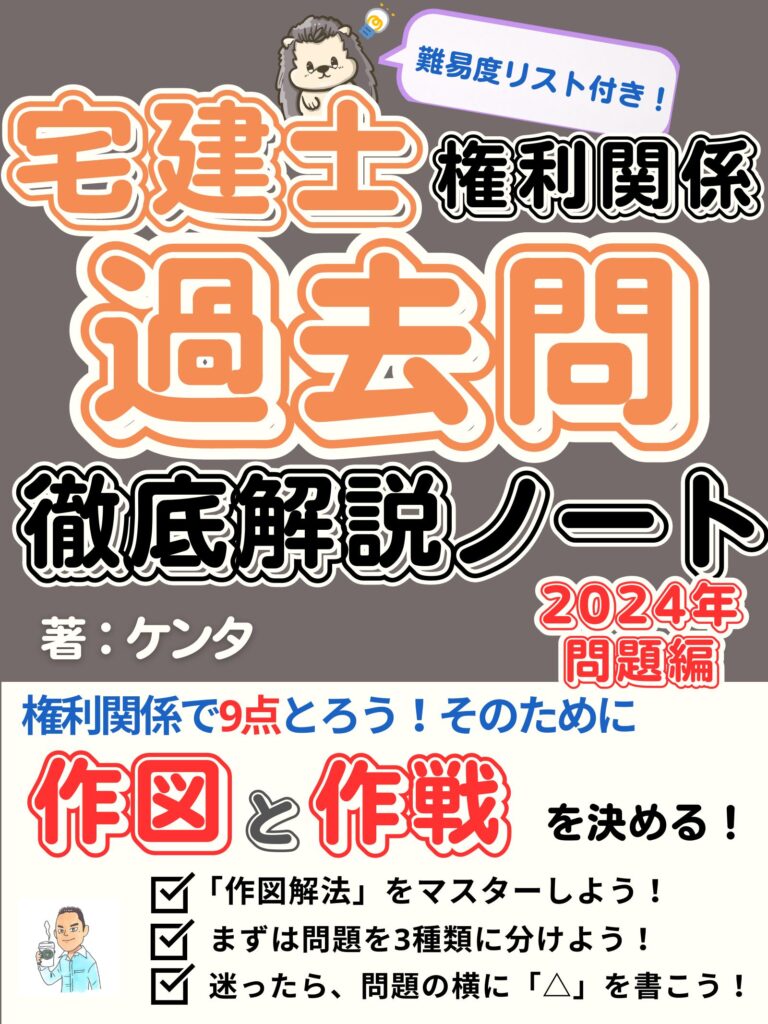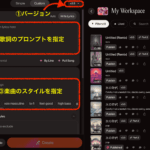宅建士の勉強時間が合計100時間を超えたときの実感
前回お伝えしたように、私は今年(2018年)の10月に宅建士を受験する予定です。
昨日、受験の手続きをしてきましたよ。
受験料が7,000円というのがリアルにきつい……。
完全なる独学で勉強をすすめていますが、やはり資格試験は精神安定上いい効果がありますね。
日々、定期的に勉強をしているので、前進している感じを毎日実感することができます。
私は手帳に勉強時間(単日と累計)をメモしているのですが、ペース把握するのにとても役立っています。
どの資格でもいいので、メンタルを少し安定させたい方は何かゴールに向かって努力する姿勢を取り戻したほうがいいかもしれません。
【関連記事】
資格の取得については、賛否両論あります。
私の場合、自分の業務に関連ある資格を勉強しているわけではないので、たとえ合格したところで何の役にも立たないでしょう、との意見もあるでしょう。
でも、それはそれでいいのです。
今回は試験まであと3ヶ月にせまって勉強時間が100時間を超えたのでここまでの過程や思ったことをシェアします。
宅建士の独学は参考書の通読からスタート
どの資格も同じでしょうが、特に独学の場合、勉強を始めてしばらくは何を勉強しているのかが分からないんですよ。
私の場合、不動産の経験も知識も皆無だったので、テキストを読んでも何について説明しているのかがさっぱり分かりませんでした。
「瑕疵」とか「専属専任媒介」などの見知らぬ単語がバンバンでてきて、早速挫折しそうになりました。
そこで、まずは全体のボリューム感をはかるために参考書を通読することにしました。
ここで大事なのは「理解しようとしないこと」。
最初に肝心なのは、宅建士の試験範囲を知ることです。
この段階においては内容を理解することに努めるのではなく、まずは宅建士がどれくらいの範囲なのかを体感してみることです。 もちろん忘れても構いません。
まずは、参考書を一周ざっくりと読んでみましょう。
ちなみに私はTAC出版の「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 2024年度」 を利用しました。
参考書の通読が終わったら、問題集を解いてみる!
参考書の通読が終わったら、インプットを強化するのが王道でしょう。
参考書の内容をノートに整理したりして、記憶を定着させるのです。
しかし、私はこの段階ではノート作りをしませんでした。
それよりも問題集を実際に解いてみてどのような問題が出題されるのかを体感しようと思ったのです。
この段階では、問題集を解くことによって正解を導きだすことは放棄しましょう。
「どのテーマやトピックが出題されやすいのか」ということを把握するために問題を解くのです。
だからここでは正解率を気にする必要は全くありません。
問題集を一回転させることで分かると思いますが、最初はまったく正解することはできません。
笑えるくらい間違えます。
でも、それでいいのです。
最初は問題の傾向をつかむことに全力をつぎ込みましょう。
ちなみに私が使ったのは「みんなが欲しかった! 宅建士の一問一答問題集 2024年度版 [宅地建物取引士 知識の確認に役立つ864問収録!」です。
独学を開始して2ヶ月経過。現在は問題集2回転目です
私が参考書の通読を開始したのが、2018年5月14日。
2ヶ月少しの間でようやく100時間をオーバーしました。
ちなみに参考書の通読が完了したのは5月31日で、合計29.5時間かかりました。
問題集を一回転させるのに、6月5日〜7月13日まで約63時間の時間を投下したことになります。
宅建士の独学の標準時間は約200時間〜300時間と言われていますが、私は法律の素人なので、350時間ほどの勉強時間を見積もっています。
あと250時間の勉強時間を確保しなければならない計算になります。
大変そうな道のりですが、それほど悲観はしていません。
1回転目よりも2回転目のほうが理解がすすむし、全体が見えてくるので、勉強としてはスムーズに行くと思っているからです。
さらに、1回転目で「どの分野を覚えるべきか」を把握しているので、2回転目3回転目でさらに焦点をしぼることができると思っています。
今後の勉強予定として問題集を3回転!
7月と8月は問題集2回転目を仕上げます。
出来れば9月半ばまでに3回転させたいですね。
その後、9月後半からは過去問3年分を2回転させようかと思います。
10月にTACの公開模試も受験する予定です。
なにせ久々の資格試験なので、試験の雰囲気に慣れておくことも必要かと思っています。
かなりタイトなスケジュールですが、また進捗などもご報告します。
★2回目の受験で合格しましたので経緯をまとめました!
★ご案内
多くの宅建士受験生が苦手とする「権利関係」。
「権利関係の14問が合否をわける!」といっても過言ではないほど重要なジャンルです。
そこで、権利関係に特化したテキストと問題集合計5冊をKindleで発売中!
ちなみに、Kindle Unlimitedなら月額980円で200万冊以上が読み放題。
30日間の無料体験もありますので、お試しください!
①「宅建作図(基礎編)(応用編)」
「基礎編」では「12の作図ルール」を紹介し、「応用編」では「債権」「物権」「賃貸借」という宅建士の頻出パートを図解しています。まずは、基本的な作図パターンをトレーニングしましょう!
②「宅建士過去問(権利関係)徹底解説ノート(2022年〜2024年問題編)」
権利関係14問のうち9問以上正解するため過去問を研究した成果を「徹底解説ノート」として発売中!
各問題の難易度や正解パーセンテージを記した「難易度リスト」も記載していますので、ご参考にしてください。
他にも「スリランカアーユルヴェーダ旅行記」や「睡眠薬の断薬記録」などの電子書籍も発売しているのでぜひご覧ください!
*「Kindleアンリミテッド」では無料で読めますので、ぜひ!
FP相談サービスなどなんでもご相談にのります!
詳しくはこちらから!
この記事を書いたのは私です

-
いまは兼業会社員ですが、2025年中に行政書士事務所を開業予定!
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多業界ですべての管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)
【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。
【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。
【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。
最新の投稿
 旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由
旅&グルメ2025年6月19日スペイン語学習をオススメする理由 家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう!
家計戦略2025年6月5日中高年こそ「地域通貨」を使おう! 旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。
旅&グルメ2025年6月3日ちょっとスペインに行くことにします。 健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。
健康2025年6月2日映画「サブスタンス」が意外と面白かった。